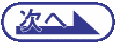付知川が現れる。朝の陽射し、きらきらと輝く水面、渓流をわたる風、そして萌えるような山の緑。
江戸時代も、杉林で暗い木曾街道より、この裏木曾街道を選ぶ旅人が、少なからずいたでしょう。
撮影していると、どこからか道路作業員さんが現れて、作業開始の立て看板を並べます。看板には、「オオキンケイギク(特定外来生物)・駆除作業中」 …? お話しを伺うと、オオキンケイギクは黄色い花をつける植物で、河川敷をあっという間に埋め尽くしてしまうという。
作業員さん「でも、けっこう綺麗な黄色の花でしてね。ここいら近所のご婦人が生け花にしてて。『おかあさん、ダメだよ、僕らはコレ伐採して燃やしてるんだから』って言ってる(笑)」
重要なお仕事だから頑張ってと、ねぎらって、彼と別れました。このあと、騎上からオオキンケイギクを目撃しました。キクというよりマリーゴールドを思わせる花でした。
江戸時代も、杉林で暗い木曾街道より、この裏木曾街道を選ぶ旅人が、少なからずいたでしょう。
撮影していると、どこからか道路作業員さんが現れて、作業開始の立て看板を並べます。看板には、「オオキンケイギク(特定外来生物)・駆除作業中」 …? お話しを伺うと、オオキンケイギクは黄色い花をつける植物で、河川敷をあっという間に埋め尽くしてしまうという。
作業員さん「でも、けっこう綺麗な黄色の花でしてね。ここいら近所のご婦人が生け花にしてて。『おかあさん、ダメだよ、僕らはコレ伐採して燃やしてるんだから』って言ってる(笑)」
重要なお仕事だから頑張ってと、ねぎらって、彼と別れました。このあと、騎上からオオキンケイギクを目撃しました。キクというよりマリーゴールドを思わせる花でした。
付知峡の倉屋温泉、「おんぽいの湯」はもう少しです。川を覗いてみると、水が綺麗。木曾は昔からヒノキやサワラなど良質な木材の生産地で、切り出した丸太をこの川に流し、木曾川経由で名古屋や三重まで運んだそうです。作業のかけ声が「おんぽいェ〜」といい、これが命名の由来という温泉。江戸時代は、付知川も水量が多かったんでしょうね。
「倉屋温泉→」の看板を左折して狭い集落のなか「おんぽいの湯→」の看板どおりに進む。たぶん、こじんまりとした温泉なんだろうな…。
突然に民家が途切れて、広大な駐車場が現れます。杉林を背にした巨大な温泉です。こっ、こんなにデカいの?
突然に民家が途切れて、広大な駐車場が現れます。杉林を背にした巨大な温泉です。こっ、こんなにデカいの?